損保子会社の春闘を考える
朝霧 悟朗
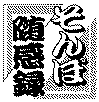
春闘の時期になると、いつも考えてしまうことがある。 ひとつは損保関連会社や子会社の労働者たちのたたかいだ。いうまでもなく総じて賃金水準は低い。たとえば、ある大手損保の子会社に勤務する二人の女性(いずれも正社員で全労連損保関連支部組合員)の年収は、残業代込みでいずれも300万円にとどくか届かないか、である。時給に直すと最低賃金ギリギリ。勤続年数10年超でこの実態である。
会社は団交の席上で、労働者たちの実態に「理解」を示しながらも、結局は「ない袖は振れない」という。会社の「売り上げ」、すなわち受注者である親会社が支払うコストは、一方的に決められた額であり、子会社にほとんど発言権はない。
こうした構図は日本社会全体に共通している。だから、賃金交渉はいつも堂々巡りになり、壁に突き当たる。
子会社や下請け会社の賃上げは、親会社の労働組合のたたかいやサポート抜きにありえない。ところが、企業労働組合幹部たちはいたって無関心である。子会社や下請け企業の置かれた立場と、そこに勤務する労働者の境遇が、実は、親会社の労働者の権利や賃金水準の足を引っ張っているという単純な理屈を理解しようとしない。関連企業で働く仲間のことを考える想像力に乏しく、人間としての温かさに欠ける。
国税庁の「民間給与実態表」によると、年収300万以下の労働者が全体の47・6%、300万円から500万円の労働者が28・5%。その割合は年々増えつつある。
一方で1億円以上の役員報酬を受けている役員は公表されているだけで240社、538人(2018年度)。ますます貧富の差が開いている。 社会的公正という観点からも、労働組合の責任は重いが、多くの企業労働組合幹部は、自らがいかに早く1億円プレーヤーになるかばかりを考えているようだから、期待するのは無理というものだ。
日暮れて道遠しだが、あふれる巷の怒りを結集して巻き返しを図りたいものだ。