
それは「働き方改革」から始まった。
まえだ いさお 元損保社員 娘のいじめ自殺解明の過程で学校・行政の隠蔽体質を告発・提訴 著書に「学校の壁」 元市民オンブズ町田・代表
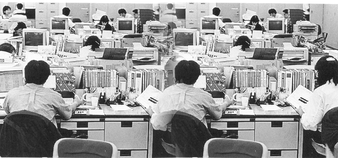
安倍政権時代、「働き方改革」という名で成立したいくつかの働き方改革関連法案。長時間労働による心身の負担が原因で、病気や自殺に至るケースが後を絶たないことをきっかけに議論が始まったはずだったが、働く人の側からよりも働かせる側の意見が多く取り入れられ「働かせ方改悪」という方がぴったりする結果になったように思う。
その中でも特に気になったのは「高度プロフェッショナル制度」。この制度は、高度な専門知識やスキルを有する働き手を対象に、労働基準法の労働時間や割増賃金に関する規定を適用しない制度である。年収1075万円以上の人を対象とすることになった。健康確保等に一定の措置を講ずれば企業側としては、残業代、休日手当などを全く支払わなくて済む。定額働かせ放題の究極版と言えば理解が速い。
残業代を全く支払わないで済むということから、導入する会社多いのではないかと注目していたが、適用された人の人数は1000人余りという。経営側にもあまり人気がないようだ。
裁量労働制は、仕事のやり方や時間配分を働き手の裁量に委ねるという名目で、事前に労使で定めた「みなし時間」だけ働いたとして賃金を払う定額働かせ放題制のひとつである。制度の趣旨からすると、何時に出勤しても何時に退勤してもいいはずだが、早朝出勤、夜8時9時退社というのが実状のようだ。また、建て前では、深夜・休日の勤務には、時間外割増賃金が支払われることになっているが、「裁量労働制だから残業代は出ない」と思い込まされていて、請求することすらしないのが実態のようだ。(裁量労働制だけでなく、「年俸制」という言葉も同じように、「年俸制だから残業代は出ない」と思い込まされている人が多い。)
いくつかの損保会社は、かなり前から裁量労働制を活用してきた。
損保業界で働く某研究者の調査によると、某社では、「当該事業場における事業戦略を策定する業務」に従事する者を「裁量労働制」の対象者とし、総合職の8割にその制度を適用していたという。そんなにたくさんの人が「事業戦略を策定する業務」に携わっていることはありえない。この会社では、この「裁量労働制」の適用者と「管理監督者」を合計すると総合職の9割、全社員で見ても45%を占めたという。
この管理監督者の多さも問題だ。労基法では、いわゆる「管理監督者」について、残業代・休日勤務手当を出さなくていいことになっている。しかし、その管理監督者とは「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」を言い、役職名で判断するものではない。つまり、課長だから「管理監督者」というわけではないのである。「経営者と一体的な立場」と考えるには無理がある課長クラスを管理監督者とするだけでなく、ラインを外され一担当者とされた元課長をも「管理監督者」として残業代を支払っていなかった。いまもその現状に変わりはないと思われる。
このほか損保某社では、就業時間中の談笑、喫煙、喫茶、化粧等の時間を,就労していない「私的時間」とみなし、それを各人のパソコンに入力させて、労働時間からカットする時間管理を行っていたという。(今もそうなのか、現役の方々からの情報提供を期待する。)
高度プロフェショナル制度が施行される数年前の記憶だが、国会で、損保会社が企画型裁量労働制を営業部門にまで適用している、これは違法ではないか、と指摘されたことがあった。(この件は、裁量労働制に関する労働時間捏造問題の陰に隠れてしまってあまり報道されなかったように思う。)指摘されて、適用対象者を大幅に減らした会社もあったが、営業担当者を「事業場外みなし労働制」に移行しただけの会社もあった。
この業界では、労働関係法規はコンプラの対象外とでも考えているのだろうか。
経団連は、上記のように問題視されるのが嫌なようで、2024 年1月、「労使自治を軸とした労働法制に関する提言」を行った。時代にあった見直しが必要だとして、労使が合意すれば、労基法などの規制を外せるようにすべきだと・・・。
裁量労働制も36協定も、労基法の例外として労使合意があれば認められる制度であるが、その他さまざまな労働条件についても、労使で決めればOKということにしようということだ。働かせ方の例外である裁量労働制や高プロを、例外ではなく原則にしてしまおうということだ。これは労基法体系の解体と言ってもいい。
そしてその提言に沿った検討が、現在、厚労省の「労働基準関係法制研究会」で急ピッチに行われている。
労使の合意があればというが、働く側の一人一人は経営側に対して対等な交渉力を持っていない。そのために労働法がある。労働者は団結し、労働組合を結成し、団体交渉や労使協議を行う権利を持っている。しかし労働組合の組織率は16%ほど。働く側の圧倒的多数が交渉力の弱い一人一人なのだ。
そんな中で、労基法が、「働く人が人たるに値する生活を営むため、雇用と労働条件の最低基準を保障するための法律」として、最低限の縛りをかけているわけである。
36協定や裁量労働などについての締結当事者は、従業員の過半数で組織される労組のある企業では労組であるが、従業員の過半数で構成される労組がない企業では、従業員の「過半数代表」でOKとされている。労組が「御用組合」というのもアブないが、それ以上にアブないのは「過半数代表」である。経営者が息のかかった従業員を指名するとか社員親睦会などの代表者が自動的に就任する等の不適切な選出が多い。ワタミでは、店長の指示でバイトが36協定に署名していたという情報もある。筆者も、たまたま関わった会社で、経営者お気に入りの従業員を「従業員代表」としますという通知文が流れているのを見たことがある。
このような実態のもとで労基法の縛りを外す「労使自治」とは、経営側の好き勝手を許すということだ。こんなことが許されてはならない。